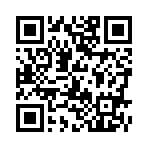旅の文学 紀行文にみる旅のさまざま
5月2日(木)@静嘉堂文庫美術館
http://www.seikado.or.jp/010100.html
※画像の建物は美術館ではなく『静嘉堂文庫』
さすが文庫=『図書館』だけあって、所蔵品に『静嘉堂文庫』と朱色の蔵書印が押してあるものがいくつかある。
中には『阿波國文庫』『不忍文庫』と、別の文庫の複数の蔵書印が押されているものもあり、興味深い。
私は紀行文には、三種類ある気がする。
1)旅のガイドブック
★たとえば『ことりっぷ』たとえば『地球の歩き方』。。。
さまざまなガイドブックがあるが、昔の人々も、やはり情報を欲していたにちがいない。
菱川師宣画の『東海道分間絵図』は、日本橋から京都までのロードマップ
地名の表記が品河(品川)、六江(六郷)と、現在と微妙に異なっている。
『江戸鹿子』は江戸 の名所旧跡にとどまらず、江戸の諸職業・諸商売について項目別に編集されていて、まるでタウンページのよう。
2)旅の記録
★SNSで友達に「みてみてー♪」と旅先の様子を伝えるように。。。
司馬江漢の『画図西遊譚』
先に発刊された『西遊旅譚』の「久能山之図」が、幕府の禁に触れて削除して再編集されたらしい。
「不適当な」何があったのか???気になる!
3)出張命令に対する業務報告書
★画も交え、現地の様子を詳細に報告。
樺太探検で教科書にも登場する、間宮林蔵の『東韃紀行』
現地の人々の暮らしの様子も伝わってくる。
今でいう国家公務員なので、帰国してから『旅費精算しなくちゃ!報告書書かなきゃなぁ。。。』って、けっこう大変だったと思う。。。w
★そして。。。漂流記
鎖国時代の日本人にとって、外の世界の様子を知るなんて、どんなにワクワクドキドキ、知的好奇心をくすぐったことか。。。
『環海異聞』
仙台藩領の若宮丸が暴風のためロシアに漂着。その乗組員の見聞記。
シャンデリアのついた舞台の上にいる男女や楽器を演奏する人々。
バレエの舞台に間違いない♪
注1)文中の敬称は、略させていただいています。
注2)あくまでも私、Girasole、個人の感想です。
注3)文中記載のURLは、許可をとっていないのでリンクを貼っていません。
続きを読む